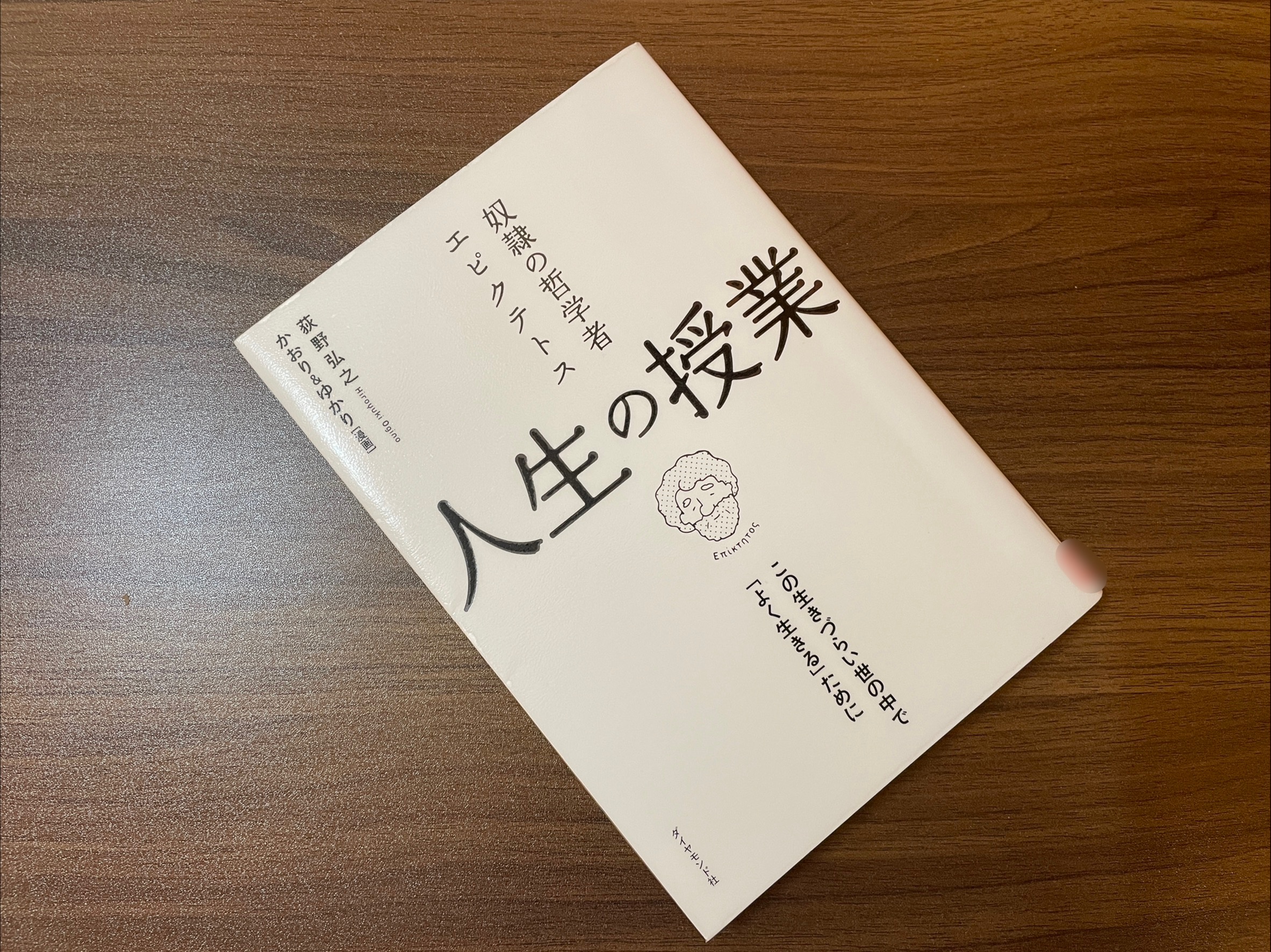この記事は
人生に行き詰まりを感じている人に読んで欲しい本
「奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業」
の紹介と、実際に私が読んだ感想を書いてあります。
以前からエピクテトスという人に興味をもっていました。
きっかけはこの本です。↓
「その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。」エピ先生に話聞いてもらおう
エピクテトスの教えを一言で言えば
自分のコントロール可能な事柄に注力せよ
ということ。
それ以外は悩んでもどうにもならないので考えない。
シンプルでありながら実に奥深い。
私はもっとエピクテトスについて知りたいと思いました。
それで今回手にした本がこちら
「奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業」
広告です
マンガでストーリを見て、関連性のあるエピクテトスの言葉に触れ、わかりやすい解説を読む。
そんな形式ですらすらと楽しく読める本でした。
※ 本ページはプロモーションが含まれています。
エピクテトス 人生の授業 大切なのは「自分次第で無いものは軽く見る 」
本書「奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業」でメインテーマは
自分次第で無いものは軽く見る
ということです。
このテーマを常に意識しながら見ていくとわかりやすいです。
自分次第で無いものは軽く見ることで人生のあらゆる悩みが解決されていきます。
心に刺さる名言もたくさんあります。
ぜひ本書を実際に手に取って読んで欲しいです。
奴隷の哲学者 エピクテトスってこんな人
エピクテトスの人生については本書24ページ
エピクテトスの生涯と著作
で詳しく記載されています。
私なりにエピクテトスについて説明すると次のとおりです。
エピクテトスは紀元1〜2世紀の人です。
今から1900年前くらい。
帝政ローマの頃の哲学者で、ローマやギリシャで活動していました。
ちなみに哲学の流派「ストア派」の代表的な人です。
エピクテトスは奴隷階級でした。
奴隷から紆余曲折を経て哲学教師となりました。
エピクテトスの著書はありません。
ですが、彼の弟子が書き残した本
「人生談義」「提要」
は残っていて、いろんな言語で翻訳されています。
マンガもあってわかりやすい! 「奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業」
本書「奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業」は哲学の本ですが難しい印象はありません。
本文は全部で27話あります。
1話ごとの構成は次の通りです。
まずマンガで登場人物たちのやり取りがあります。
主な登場人物は当然エピクテトス先生、そして本書の主人公と言うべき奴隷のニウス君。
さらに彼らを取り巻く人たちがその都度登場します。
最初にマンガでニウス君が悩み、グチを言ったり、気分を害したり、落ち込んだりします。
そんなニウス君のモヤモヤをエピクテトス先生がズバッと切っていくわけです。
次に先生の弟子アリアノスが編纂した「提要」からマンガエピソードに係る部分が紹介されます。
最後に著者の現代社会に即した分かりやすい解説があるわけです。
「提要」を読んで
「ん?なんのこっちゃ?」
と思う事があってもご心配なく。(私はたびたびありました)
1話ごとにある著者の解説でよくわかります。
私のように哲学の「て」も知らないような人でも最後まで読み切れました。
大丈夫です!
奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業 ハイライト
ここからは本書「奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業 」について、私が個人的に心に刺さった事を取り上げていきます。
心に刺さった言葉は次の通りです。
- 人を不安にさせるのは事柄ではなくそれに対する考え方
- 人にどう思われようと、自分が自分をどう思うかだけで充分
- 問題はその人の行いよりも何故それをしたのか?
- 快楽は手短に片手間に
- 恐ろしい事、とりわけ死を常に意識する
以下、それぞれについて見ていきましょう。
1 人を不安にさせるのは事柄ではなくそれに対する考え方
主人公のニウス君は奴隷階級です。
そして、ご主人さまがおっかないので会うたびにびくびくしています。
一方、ニウス君の同僚は恐れることなくご主人さまに自分の事をアピールしています。
その様子をみてエピクテトス先生はニウス君を諭すのです。
ニウスを怖がらせているのはご主人さまでは無くニウス自身だと。
人々を不安にするものは、
事柄それ自体ではなく、
その事柄に関する
考え方である
第8話「怖い・・・怖い・・・」 より引用
私にも何度も似たような事がありました。
会社の上司や学校の先生。
怖い人っていますよね。
でも、一方では怖くないと思っている人も確かにいました。
もちろん上司や先生のこちらに対する接し方もあるでしょうけど。
基本的には
上司が怖いのではない。上司が怖いと思っている自分がいる。
そう言うことなんですね。
2 人にどう思われようと、自分が自分をどう思うかだけで充分
主人公のニウス君が奴隷仲間の飲み会に気が進まないままに参加します。
仲間から嫌われたくないからでした。
次の日は二日酔い。
そこをエピクテトス先生に諭されます。
誰かに気に入られたいということばかり考えてしまうと自由を失ってしまいます。
他人にどう思われるかではなく
自分自身に
そう思われるだけでよい。
それで十分である。
第16話「みんなに嫌われたくない・・・」 より引用
という事になるわけです。
私も過去職場のイヤな飲み会に参加していました。
「これも給料のウチ」と言い聞かせて。
ニウス君と同じです。
他にも「嫌われたくない」なんて場面は多々ありますけど、結局は自分自身が自分をどう思っているかだけなんですね。
人にどう思われようと、自分が自分をどう思うかだけで充分 なんです。
3 問題はその人の行いよりも何故それをしたのか?
ある男が真昼間から酒に酔いつぶれて路上で寝ていました。
ニウス君はそれを「だらしない」と思いました。
でも本当にだらしないのでしょうか?
当人の考えをきちんと
識別しないうちに、
それが本当に悪いかどうかを
君はどこから知るのかね
第17話「道端にいた酔っ払い」 より引用
その酔っ払いの行為は褒められたものではないでしょう。
でも、その男は単に酒にだらしない男とどうして言い切れるのでしょうか?
もしかしたら最愛の妻を病気で亡くしたのかもしれない。
一夜のうちに全財産が消失したのかもしれない。
もし、そんな事情があってもその男を単に「だらしないヤツ」と言い切れるのか?
これには私は考えさせられました。
この例に限らずそんなことっていろいろありますよね。
運転していて無理な割り込みされたり。
コンビニで店員さんの態度が悪かったり。
問題は行為自体では無くてどうしてそうしているのか?
態度が悪い店員さんがいた。事実はそれだけ。
その人の行いよりも何故それをしたのか?
そのことを詳しく知りもしないで良い悪いなんてわかるわけがない。
そう考えるとなんだか冷静に対処できる気がします。
4 快楽は手短に片手間に
私は快楽を捨てられません。
もうどうしようも無い!
エピクテトスはストア派の代表的な哲学者です。
ストア派の「禁欲主義」なんて言われます。
でも、エピクテトス先生は厳しく禁欲を唱えているわけでもありません。
これらの快楽に「長い事時間を費やすな」と戒めているだけです。
第23話「心に目を向けるようになったら・・・」 より引用
快楽は手短に片手間に ということ。
それなら私にもできそうです。
夜遅くまでYouTubeをダラダラ見ないで時間や制限を決める。
これくらいなら何とかなりそうです。
5 恐ろしい事、とりわけ死を常に意識する
「自分次第で無いものは軽く見る 」のであれば死もまた軽く見るしかありません。
遅かれ早かれ、人はいつか必ず死ぬからです。
私も含め、一般的に人は自分が死ぬことを忘れて生きています。たぶん。
限りある人生という感覚が無いので日常のしょーも無い事に一喜一憂してしまいます。
エピクテトスは言います。
死や追放や、その他何でも「恐ろしい」と思える事柄を、毎日のように君の眼前に置くようにするがいい。その中でもとりわけ死を。そうすれば、君は決して卑しいことを考えたりしなくなるだろうし、度を過ごして何かを欲望することもないだろう。(『提要』21)
第26話「もうすぐこの世を去るなら」 より引用
本書の解説にありますが、人は死を生まれる瞬間と死ぬ瞬間を体験できません。
生まれた時は当然記憶にないし、死ぬ瞬間には意識はありません。
だから死を恐れる必要は無いのだというわけです。
でも、「死」について恐れなければならないものがあると私は思います。
それは人は必ず死ぬ、人生にはタイムリミットがあるということ。
本書を読んで、私は死とはタイムリミットなのでは無いかと思いました。
だからこそ、
「毎日のように君の眼前に置くようにするがいい。その中でもとりわけ死を。 」
が私にはタイムリミットとしてストンと心に落ち着きました。
もちろん死が怖くないとは思いません。
でも、次の文章を読むと怖がってばかりもいられません。
いつか自分は必ず死に、消え去るのだと想えば、いたずらな欲求に振り回されることはない、というのがこの章でのエピクテトスの眼目である。死を想えば、地位や名誉、財産など、これらを得るために人生を棒に振ることがいかにムダなことかがわかるだろう。
第26話「もうすぐこの世を去るなら」 より引用
私にとって死はタイムリミット。
くだらないことに思い悩んでいる場合じゃないんです。
毎日生きていく上で死を常に意識するということはタイムリミットを意識すること。
そして日々を大切に生きる事だと感じました。
広告です。
まとめ エピクテトスの教え 私に刺さった5つの名言
本書「奴隷の哲学者 エピクテトス 人生の授業」のメインテーマはやはり
「自分次第で無いものは軽く見る 」
こと。
真に自由に生きたいならばここからはじめる。
それがエピクテトス先生の教えなのです。
本書にはその他にも心に刺さる名言がいっぱいあります。
その中で私が取り上げるとすると次の通りです。
- 人を不安にさせるのは事柄ではなくそれに対する考え方
- 人にどう思われようと、自分が自分をどう思うかだけで充分
- 問題はその人の行いよりも何故それをしたのか?
- 快楽は手短に片手間に
- 恐ろしい事、とりわけ死を常に意識する
詳しくはぜひ本書を手に取ってご覧ください。